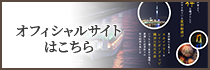すしの日本史~「押す」から「握る」へ~
令和の時代を生きる私たちが食べる寿司の定番「にぎりずし」は
いつごろ確立したのでしょうか?それも江戸時代の出来事です。
日本のすしの歴史は
「箱漬け」「箱ずし」「押しずし」「いなりずし」「にぎりずし」と変遷してきました。
その歴史をさかのぼると、奈良時代。
アワビや貝を発酵させて作るもので
室町時代には「なれずし」が登場します。
「なれずし」は、現在の日本にも残っているものです。
一例を挙げますと、よく知られているのは、滋賀県琵琶湖の「鮒ずし」。
魚のご飯漬けといったもので、飯の乳酸菌発酵を巧みに利用して
酸味のついた魚を保存食とするもので、つよいにおいが特徴です。
これが、箱に詰めて売られるようになり
さらに、早く作るためにはどうしたらよいか?という発想から
「にぎりずし」が誕生します。
このことは、それ以前にあった「すし」の概念を根底から覆すもので
画期的なことでもあったようです。
ひとくちサイズでいろいろな種類を選ぶことができ
卵焼き、車海老、海老そぼろ、白魚、まぐろ、こはだ、あなご甘煮、海苔巻き
等があったといいます。
値段はみな8文。新生姜の酢漬け、姫蓼が添えられ
仕切りとして熊笹が飾り切りにしていたようです。
まさに、今のにぎりずしと同じ様相です。
「有限会社 船宿 釣新」では
隅田川の屋形船を食事とともにお楽しみいただけます。
お問い合わせはこちらから