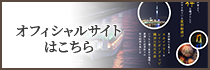江戸時代のてんぷらの食べ方~熱々をほおばるのは今と同じ~
江戸時代、人々が実際にどのようにして
天ぷらを味わっていたのかを知る手立てとして川柳があります。
「天ぷらの みせにめど木を 立てて置き」
めど木とは、占い師の筮竹(易占で使われる長さ30㎝程度の竹のひごのようなもの)のことで
この筮竹は本来、「めど萩」という植物の茎を用いていたので、そう呼ばれていましたが
のちに竹で代用するようになっていきました。
また、串にさして食べやすくし、手が油で汚れるのを防ぐという工夫も
このころにもあったアイデアなのだと思うと、感慨深くなりますね。
串にさして作る天麩羅用の竹串が、筒に差して入れられている筮竹と似ているため
このような句ができたのだといわれています。
「天麩羅」という料理名は、長崎での南蛮料理に由来し
京都を経て江戸に伝わったころには、現在の天麩羅のスタイルが定着していたといいます。
もうひとつの川柳をご紹介しましょう。
「てんぷらの 指を擬宝珠へ 引んなすり」
擬宝珠(ぎぼうし)とは、橋の欄干の柱の上にある飾り物のことで
銅板で細工したものが多くあったそうですが
橋のたもとで開業していた天ぷら屋台がけっこうな数あったのかもしれません。
この句は、天麩羅を食べたあとの油のついた指をなすりつけて
橋の擬宝珠についた油のあとの情景が表現されたものです。
どちらも、江戸の人々の愛嬌ある一面をのぞかせる句ですね。
江戸にまつわる人々の情景は、今も昔もあまり変わらないのかもしれません。
隅田川の屋形船「船宿釣新」は、食事とともにおそんな江戸時代の風流を思わせてくれます。
お問い合わせはこちらから