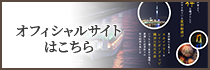江戸時代のファストフードのひとつ「天ぷら」
盛り場に、縁日に、「百万都市江戸」埋め尽くしたファストフード屋台から
いまや日本料理を代表する「天ぷら」「寿司」「そば」が生まれました。
幕末の江戸の土地について書き記した文献に
「江戸名所図絵」(斎藤長秋ら 1834年~1836年《天保5~7年》)というものがあります。
そのなかの「領国広小路」では、大川(隅田川)にかかる両国橋と
その他元の広小路、また川面にも船が出て、人々が集い
夏の一夜を見て過ごす様子が描かれています。
ついでながら、1652年《慶安5年》の8月、江戸の町では花火が禁止されたのですが
大川岸の花火だけは例外となっていたようです。
人々がそれをいかに楽しみにしていたかが、なんだか想像できます。
こうした盛り場や祭礼、縁日、花火見物に出てくる人々を目当てに
たくさんの屋台が並び、川岸の上まで食べ物が売られていたようです。
100万人以上にふくれあがった江戸の町では
18世紀半ばになると、盛り場にはそうめん売り、スイカの裁ち切り
虫売り、白玉売り、蒲焼屋、幾世餅売り、茶店などの店が出たほか
大道芸、芝居、見世物、相撲、開帳、書画会なども行われたと
便県に記録が残っているそうです。
江戸のこうした文化は、260年余りをかけて醸成されましたが
江戸後期から明治にかけてのようすも知ることができます。
そこには、やはり寿司に天ぷら、担ぎ売りのしるこ
水菓子(果物)の切り売りなどのようすが、絵に記されています。
祭礼や花火見物などに出かけて
屋台で食べる外食は、江戸時代の人たちにとっても
大きな楽しみのように感じられます。
「有限会社 船宿 釣新」では
屋形船のツアーで、江戸の風流なひとときをお楽しみいただけます。
お問い合わせはこちらから